こんにちは!
「公務員のための生活術ブログ」運営者のクロです。
今日は、公務員でも無理なくできる【王道の節税術3選】を紹介します!
ここで、
「公務員が節税なんてしていいの?」
と気になる方もいるかもしれませんが、
節税はルールの範囲内で認められている正当な権利です!
私としての考えは、「4,公務員が節税してもいい理由」にてお話します。
それでは、さっそくご紹介していきます!
1. 公務員のふるさと納税|税金控除と返礼品でお得!
ふるさと納税は、自分の好きな自治体に寄付をすると、所得税と住民税が控除される制度です。
自分が住んでいる都道府県や市町村にて働く公務員にとっては、
ふるさと納税をする = 税収を下げる行為!?
と感じて、ふるさと納税をする行為に懸念している方もいると思います。
個人的には、「自分にゆかりある自治体を応援して何が悪い?」という考えです。
・県外の大学に通っていた
・昔は別の都道府県で住んでいた
・親の実家が他の都道府県、など
自身が所属する自治体とは別のところにゆかりや恩義を感じ、ふるさと納税を行うことに何の問題も無いと思っています。
使える制度は積極的に使って、家計を守っていきましょう!
✅ 制度とメリット
- 実質2,000円の負担で、寄付金額に応じた控除が受けられる
- 地域特産品などの豪華な返礼品も受け取れる
- 手続きも「ワンストップ特例制度」でカンタンに完了できる
【参考リンク】
👉 ふるさと納税ポータルサイト_よくわかる!ふるさと納税:総務省
✅ 利用しないとどうなる?
たとえば年収400万円の公務員の場合、
年5万円分の寄付=約48,000円の節税ができる可能性があります。
(※家族構成、所得控除などの要素により個人差あり)
これを使わないと、実質【毎年数万円分の「損」】になることに…。
2. 公務員のNISA活用術|非課税で投資デビュー
NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益に通常かかる約20%の税金が非課税になる制度です。
2024年から「新NISA」がスタートし、制度がさらに使いやすくなっています!
株式などの資産運用は公務員のできる副収入を得る方法の一つです!
「株はギャンブル」と思われる方もおられるかもしれません。
個人的に、株式がギャンブルという考えに対しては「使い方次第」という考えです。
例えば、調理道具の包丁は料理をするためのものですが、人を傷つけることもできます。
これと同じように、株は本来将来に向けた“投資”ですが、ギャンブルのようにすることもできます。
株を初めて始める人は、何を買ったいいかわからない方もおられると思いますが、ネットで軽く調べただけでも「優良なインデックス投資をしよう」とよく出てくると思います。
“長期・積立・分散”を守れば、そこまで恐れることはないと、個人的には思います。
公務員の給料は、劇的にアップするようなことはありません。
なので、その代わりにお金に働いてもらいましょう!
✅ 制度とメリット
- 年間360万円(トータル1,800万円)まで投資でき、得た利益が非課税
- 積立投資が基本なので、初心者でも始めやすい
- 使わない現金を有効に活用できる
【参考リンク】
👉 NISA特設ウェブサイト_NISAを知る:金融庁
✅ 利用しないとどうなる?
仮に10年間で50万円の利益が出たとき、
通常なら約10万円(20%)が税金で引かれます。
NISAを使えば、この税金で引かれる10万円を丸ごと受け取れるので、
使わないと長期的に大きな差になります!
3.公務員のiDeCo解説|節税&老後資金を両立!
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で積み立てる年金制度で、掛金が全額所得控除されます。
個人的には、もうすぐ年金をもらえる年齢であれば特にする必要はないと思います。
しかし、20~30代は特に年金額に期待できないですので、積極的に利用していくべきと思います。
ただ、注意点として、引き出せる時期がかなり先の話になってしまいますので、無理のない範囲での掛け金に設定するべきかなとは思います。
また、iDeCoも運用先の多くは株式や債券の投資信託ですので、NISAのように多少の株の知識等が必要となります。
✅ 制度とメリット
- 掛金がそのまま所得控除=住民税・所得税が安くなる
- 運用益も非課税
- 将来の年金額を自分で増やせる
【参考リンク】
👉 iDeCo公式サイト_加入希望者の方へ
※注意点:公務員のiDeCoは、2024年の改正により月額20,000円まで拠出可能です!
✅ 利用しないとどうなる?
例えば、月2万円をiDeCoで積み立てると、
所得税・住民税が年間約48,000円ほど減る計算に(年収400万円の場合)。
これをしないと、毎年数万円レベルで税金を多く払うことになります。
✅ 公務員が節税してもいい理由
個人的に、税金を3種類に分けて考えています。
① 絶対に納めないといけない税金
② 納めなくていい税金
③ 納めてもいいし、納めなくてもいい税金
私にとっての“節税”は、③「納めてもいいし、納めなくてもいい税金」について「絶対に納めないようにする」というものです!
簡単な例で説明すると、
「確定申告で手続きすれば所得税の還付金がある」
という状況では、少し手間であっても「確定申告をする」という選択をすることを“節税”と呼んでいます。
①のような納めないといけない税金を払わないようにすることは、“節税”ではなく“脱税”です。
「決められた制度を正しく利用して税負担を減らすこと」に何も問題はありません。
むしろ、「自分と家族を守るための大切な行動」と言えるでしょう!
安心して、上手に使っていきましょう!
✨まとめ|今日からできる節税を始めよう!
今回は、
「ふるさと納税・NISA・iDeCo」という王道節税術3選をご紹介しました!
どれも難しいものではありません。
できることから1つずつ始めるだけでも、将来への安心感が大きく変わります。
ぜひ、あなたも今日から一歩踏み出してみてくださいね!
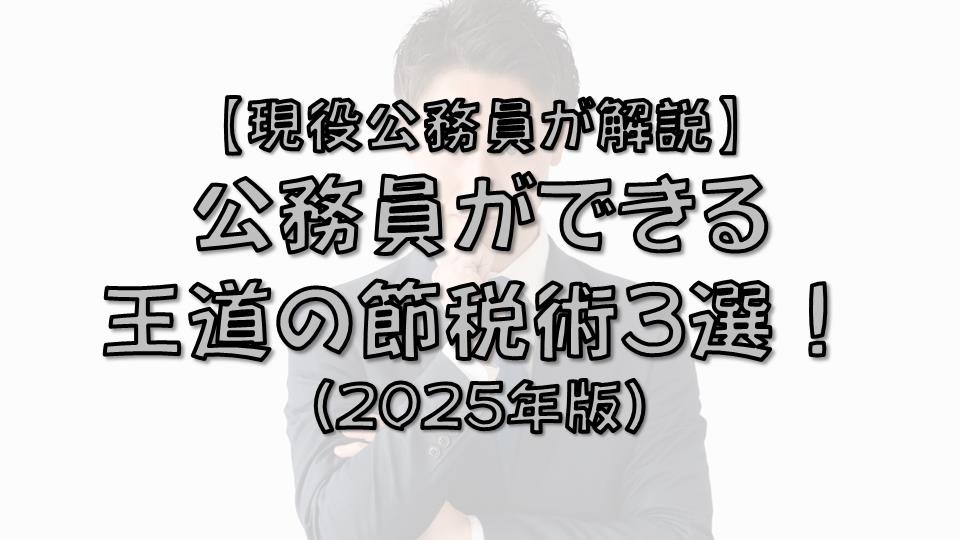
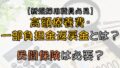
コメント