こんにちは、
「地公のトリセツ」運営者のクロです。
節税や老後の資金準備として、
iDeCo(個人型確定拠出年金)があります。
iDeCoといえば、
60歳から受け取れる制度
として知られていますが、
老後以外の万が一の出来事にも
対応していることはご存じですか?
実は、iDeCoには、
・「老齢給付金」
・「障害給付金」
・「死亡一時金」
・「脱退一時金」
といった給付方法があります。
今回は、それぞれの受給方法とその条件、
そして税金の扱いについて
わかりやすく解説します。
1. 老齢給付金
● 受給開始年齢等
- 原則、60歳から受け取れます。
- ただし、受給には“通算加入者等期間”が10年以上必要です。
- 通算期間が10年未満の場合は、以下のように受給可能年齢が繰り下がります:
- 8年以上10年未満:61歳から
- 6年以上8年未満:62歳から
- 4年以上6年未満:63歳から
- 2年以上4年未満:64歳から
- 1月以上2年未満:65歳から
- 60歳以降に加入した人は、加入から5年以上経過で受給可能です。
- 75歳までに請求が必要で、請求しないと法務局に供託されます。
● 受給の方法
(1) 年金方式(5〜20年の有期年金、または一部運営管理機関で終身年金)
(2) 一括受取方式(一時金として一括受取)
(3) 併用方式(一部一括+残り年金)
※運営管理機関によって受取方法に違いがあります。
2. 障害給付金
● 受給開始年齢等
60歳になる前に傷病によって障害状態となり、1年6ヶ月継続した場合などに、国民年金の障害基礎年金に該当する等級に認定されれば受け取れる給付です。
● 受給の方法
基本的に老齢給付金と同様で、年金・一時金・併用が可能です(運営管理機関に要確認)。
3. 死亡一時金
● 受給開始年齢等
加入者が亡くなった場合、遺族が受け取ることができる給付です。
- 受取人の指定が可能です(指定しない場合は法定順位)
- 請求は死亡日から5年以内、それ以降は相続財産となり、さらに請求がない場合は法務局に供託されます。
- 企業型DC(企業型確定拠出年金)から転職等によりiDeCoへ資産が自動的に移された方も対象です。
● 受給の方法
受給は一括受取方式(一時金として一括受取)のみです。
4. 脱退一時金
● 受給開始年齢等
原則、iDeCoは中途解約できませんが、以下の条件をすべて満たせば、脱退一時金の請求が可能です。
- 60歳未満である
- 企業型DC加入者でない
- iDeCo加入資格がない(例:保険料免除者や海外移住者など)
- 日本国籍を持つ海外居住者でない
- 障害給付金の受給権者でない
- 通算拠出期間が5年以下、または年金資産が25万円以下
- 資格喪失から2年以内
請求方法は個人の状況に応じて異なるため、詳細は運営管理機関で確認が必要です。
● 受給の方法
受給は一括受取方式(一時金として一括受取)のみです。
5. 税金の取り扱いについて
● 老齢給付金(年金方式)
- 課税対象:所得税
- 所得区分:雑所得(年金控除の対象)
● 老齢給付金(一時金方式)
- 課税対象:所得税
- 所得区分:退職所得(退職所得控除の対象)
● 障害給付金
- 課税対象:非課税
- 所得区分:非課税(障害年金等と同じ扱い)
● 死亡一時金
- 課税対象:相続税
- 所得区分:みなし相続財産(生命保険金と同様の扱い)
● 脱退一時金
- 課税対象:所得税
- 所得区分:一時所得(50万円の対象)
まとめ
iDeCoは「老後資金」としての老齢給付金が注目されがちですが、それ以外にも万が一のときに支えてくれる給付制度が整っています。
有名な制度でも意外な活用方法があったりします。
制度を正しく理解して、しっかり老後に準備しておきましょう!
※今回の記事の作成においては、以下のiDeCo公式サイトを参考にしています。
- iDeCo公式サイト「加入者の方へ」:https://www.ideco-koushiki.jp/join/benefits.html
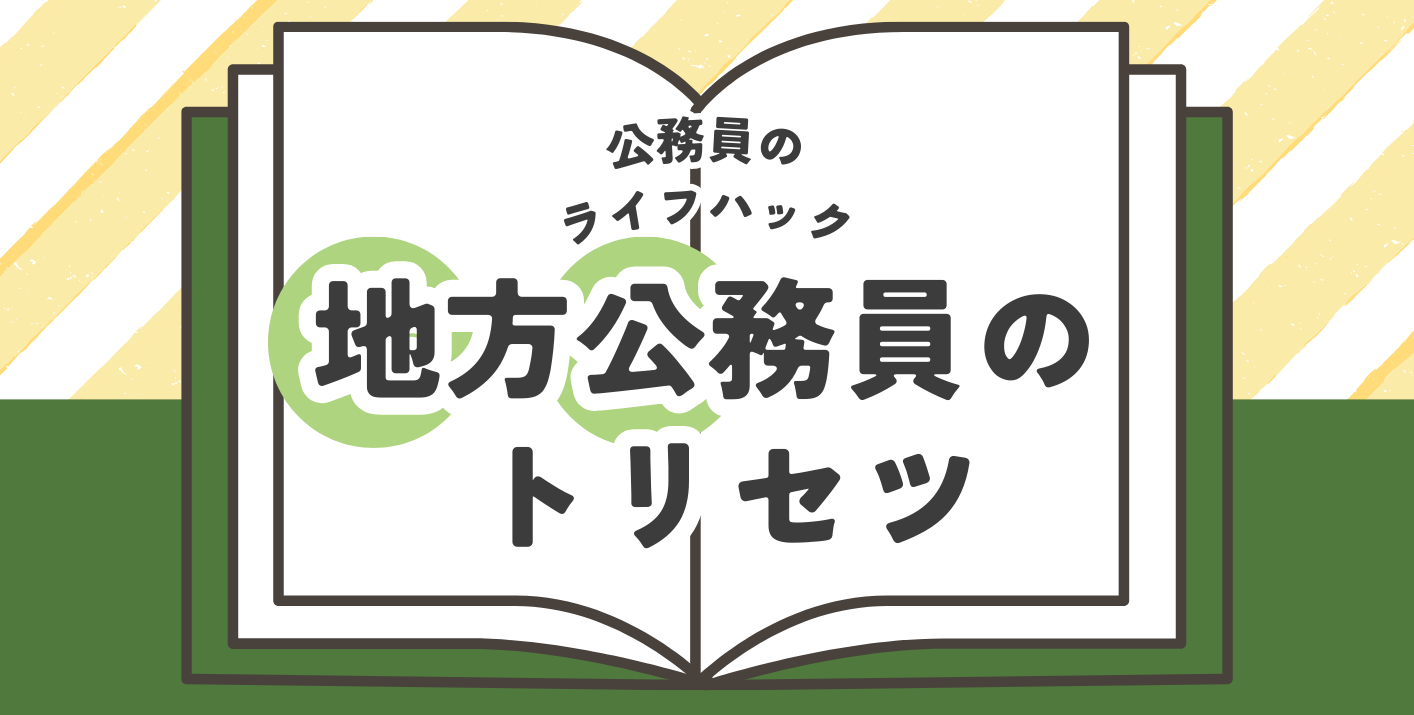
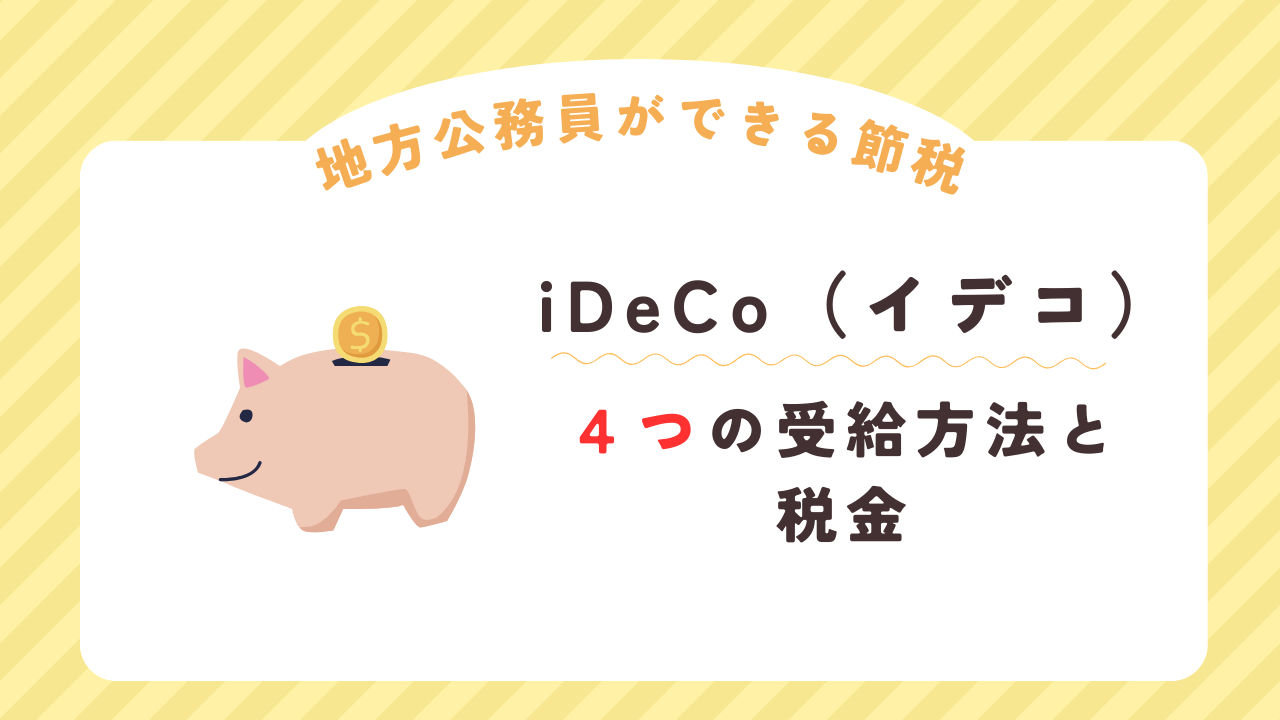


コメント