こんにちは、
「地公のトリセツ」運営者のクロです。
今年も人事院勧告の時期がやってきました。
「給料が上がるらしいけど、実際どれくらい?」
「他にどんな制度が変わるの?」
そんな疑問を持っている方も
多いのではないでしょうか?
今回は、令和7年の人事院勧告の中から、
押さえておきたいポイントを解説します。
給与アップの裏事情や、新しく導入される制度、
働き方の変化までまとめていますので、
ぜひ最後まで読んでみてください。
官民較差:15,014円(3.62%)アップ
報告文・勧告分の40ページ
今年の勧告で発表された官民較差は、
15,014円(3.62%)です。
この差を埋める形で月例給が引き上げられます。
特に若手は初任給がぐっと改善され、
一般職の大卒初任給は 、
232,000円(+5.5%) です。
…と聞くと、
「おお、けっこう上がるじゃん!」
と思うかもしれません。
しかし、
総務省の消費者物価指数(CPI)を見ると、
2024年の物価上昇は全国平均で約3%、
食品や光熱費に限れば4%台の上昇です。
つまり、給料の伸び(3.62%)は、
生活必需品の値上がりに追いつくかどうか…
というレベルです。
給与が増えるのは確かにありがたいですが、
「実質的に生活が楽になるか?」というと
少し疑問が残ります。
官民比較の対象企業規模が「50人以上」→「100人以上」に
報告文・勧告分の11ページ
給与比較の基準となる民間企業の規模が、
「50人以上」から「100人以上」
に見直されます。
対象企業が大きくなることで、
公務員の給与水準がより大企業の水準に
近づきやすくなります。
これは朗報ではありますが、
実は「新しい優遇」ではなく、
約20年前に戻っただけの話です。
小泉政権時代、給与抑制の一環として
対象企業規模が、
「100人以上」から「50人以上」に
引き下げられました。
今回の変更は、
その基準をようやく元に戻したという位置づけです。
勤務時間・休暇制度のさらなる見直し
報告文・勧告分の18ページ
勧告では、育児・介護などに限らない、
職員の様々な事情に応じた
無休の休暇による勤務時間の短縮等を
可能とする必要性が書かれています。
無給休暇のメリットは、
共済組合に加入したまま休めるというところ。
つまり健康保険・年金の資格が途切れません。
どのような制度になるかはまだ未定ですが、
心強い制度になることを期待しています。
兼業制度(自営兼業)の見直し
報告文・勧告分の15ページ
これまで制限が多かった公務員の兼業ですが、
今回の見直しで、
兼業制度(自営兼業)の範囲が広がり、
兼業(副業)の自由度が広がるかもしれません。
たとえば、
- 職員の知識や技術を生かした活動
- 執筆やYouTubeなどの発信活動
こうしたことが、
よりやりやすくなる可能性があります。
詳細については今後決まるようなので、
注目していきたいところです。
その他の改正ポイント
給与改定関連
- 本府省業務調整手当の引上げ・対象拡大
- 特地勤務手当の調整額廃止
- 徳地勤務手当に準ずる手当の支給対象の拡大
制度改正・新設
- 在級期間制度(昇格待機期間)の廃止
- 通勤手当の距離区分見直し
- 駐車場利用手当の新設
- 最低賃金との差額補填手当の新設
まとめ
令和7年度人事院勧告については、
人事院のホームページで確認できます。
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r7/r7_top.html
今回の勧告は、給与アップや制度改革など、
前向きな内容が多く含まれています。
変わりゆく制度を把握し、
公務員生活を楽しんでいきましょう!
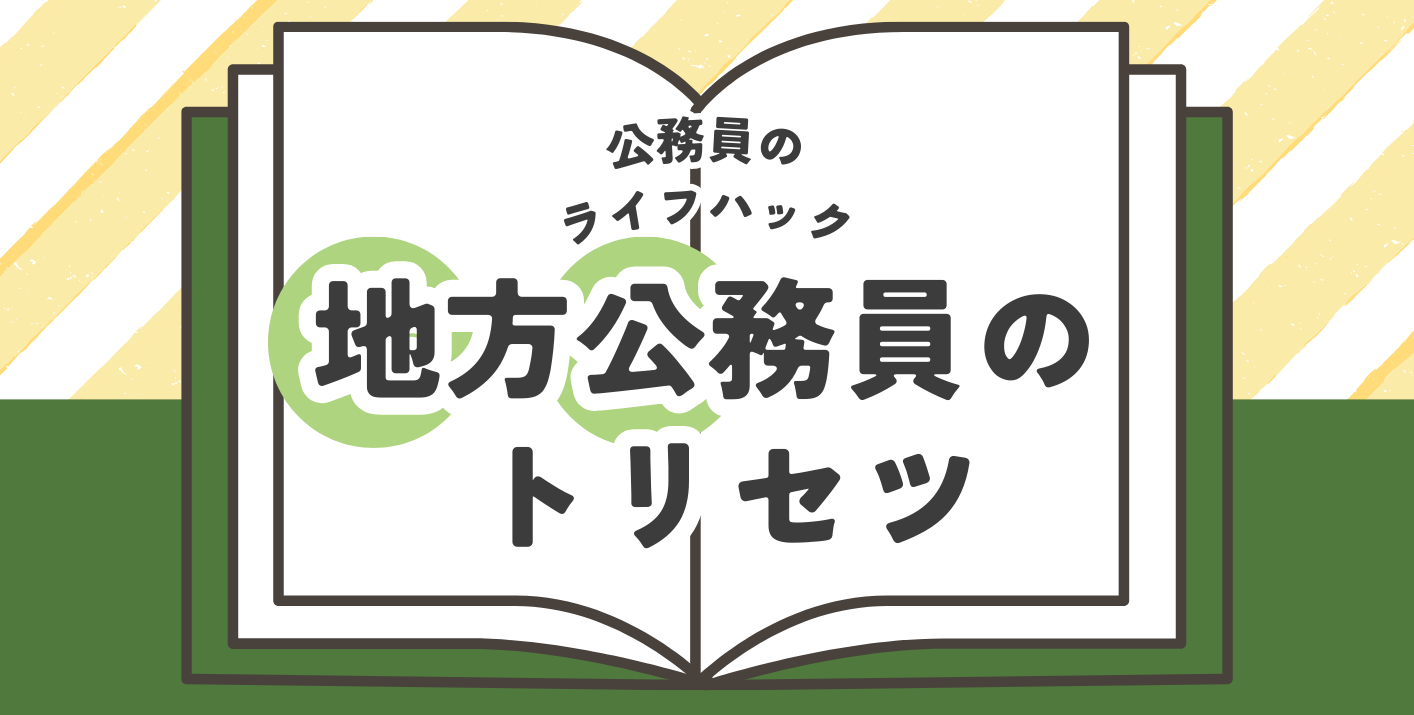

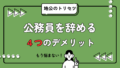

コメント